生成AIに興味があるけれど、「なんだか難しそう…」と感じていませんか?ご安心ください!この記事では、生成AIを使う上でよく耳にする専門用語を、初心者の方にも分かりやすく解説します。
これらの言葉を理解すれば、生成AIをもっと楽しく、もっと効果的に使いこなせるようになるはずです。
今からならまだ間に合う生成AI。まだ使ったことがない人もぜひこの記事を読んで生成AIを使ってみて下さい。
これだけは知っておきたい!必須の5つの基本用語

まずは、生成AIを使うなら絶対に覚えておきたい5つの用語からご紹介します。これらは、日々の利用で頻繁に登場する言葉なので、しっかりとマスターしておきましょう。
LLM(大規模言語モデル)
LLMは「Large Language Model(大規模言語モデル)」の略で、AIの「脳」にあたる部分です。 「どんな質問にも答えてくれる、図書館のベテラン司書さん」 をイメージすると分かりやすいかもしれません。膨大な本(テキストデータ)を読んで得た知識で、人間のように自然な文章を理解したり、書いたり、要約したりすることができます。
いわゆる生成AIのことは基本的にLLMのことを指しています。
プロンプト
プロンプトとは、AIへの「指示文」や「お願い」のことです。 「優秀なアシスタントへの仕事の依頼メモ」 を想像してみてください。
「今日の夕飯の献立を考えて」
とだけ書くより
「冷蔵庫にある豚肉と玉ねぎを使って、30分で作れる中華料理の献立を3つ提案して」
と具体的に書く方が、期待通りの答えが返ってきますよね。AIも同じで、プロンプトが具体的であるほど、質の高い結果を出してくれます。
ハルシネーション
ハルシネーションとは、AIが「もっともらしい嘘」をついてしまう現象です。 これはまるで 「知識は豊富だけど、たまに記憶違いをする博識な人」 のようです。
悪気はなく、サービス精神から間違った情報でも自信満々に「日本の首都は大阪ですよ」と答えてしまうことがあります。そのため、AIの回答が本当に正しいかは、必ず人間が確認することが大切です。
トークン
トークンは、AIが言葉を処理するときの「最小単位」です。 「AIが言葉を理解するためのパズルのピース」 のようなものだと考えてください。
AIは文章全体を一度に理解するのではなく、このピースを組み合わせて意味を解釈しています。電話料金が時間で決まるように、AIの有料サービスでは、このピース(トークン)の数に応じて料金が決まることがあります。
コンテキストウィンドウ
コンテキストウィンドウとは、AIが一度に「記憶しておける情報量」のことです。 これは 「AIの作業机の広さ」 で考えると分かりやすいでしょう。
机が広ければ広いほど、たくさんの資料(過去の会話や情報)を一度に広げて作業できるため、複雑で長い話の文脈もしっかりと理解してくれます。この机が狭いと、少し前の会話の内容を忘れてしまうことがあります。
さらに知っておくと便利な8つの専門用語

ここからは、生成AIをもっと深く理解し、より高度な活用を目指す場合に役立つ用語をご紹介します。
マルチモーダルAI
テキスト(文字)だけでなく、画像、音声、動画など、複数の形式のデータを同時に理解できるAIです。 まさに 「目と耳と言葉を全部使える超有能なアシスタント」 のような存在。
マルチモーダルなAIでは冷蔵庫の中の写真を見せながら「この食材で何か作れる?」と声で質問するような、未来のコミュニケーションが可能です。
プロンプトエンジニアリング
AIから最高のパフォーマンスを引き出すために、プロンプト(指示文)を工夫する技術のことです。 これは 「優秀な部下への的確な指示出し術」 に通じるものがあります。
ただ「資料を作って」と頼むより、「〇〇社向けの提案資料を、来週の会議で使えるように、要点を3つに絞って作って」と指示する方が、良いものが出来上がるのと同じです。
最近ではAIの性能が向上したためアバウトな指示文でも優秀な回答をしてくれるようになり、重要性は下がってきましたが、的確な指示(プロンプト)の方が回答の精度は上がります。
ファインチューニング
汎用的なAIに特定の専門知識を追加で学習させ、専門家として育てることです。 「何でもできる新入社員を『経理のプロ』に育てる」 様子を思い浮かべると分かりやすいです。
RAG(検索拡張生成)
AIが回答する前に、インターネットや特定の文書など、外部の最新情報を調べてから答える仕組みです。 「質問されたら、まず最新の参考書で調べてから答えてくれる真面目な秀才」 をイメージしてください。
これにより、AIが学習していない最新のニュースや情報についても、正確に答えることができます。
グラウンディング
AIの回答に「根拠」や「出典」を持たせる技術です。 人間の世界で言えば、 「レポートで『参考文献』を明記する」 ことに相当します。
AIの回答がどの情報源に基づいているかを示すことで、ハルシネーションを減らし、情報の信頼性を高めます。
温度(Temperature)
AIの回答の「創造性」や「遊び心」を調整するツマミのようなものです。 「会話相手のテンション調整ツマミ」 を想像してもらうと良いでしょう。
値を低くすると、教科書通りの正確で真面目な回答になります。高くすると、ユニークなアイデアや冗談を交えた、よりクリエイティブな回答が出やすくなります。
Top P / 8. Top K
どちらも、AIが次に生成する言葉の「選択肢の幅」を調整するパラメータです。専門的なので、「回答のユニークさを調整する機能」 と覚えておけば十分です。
選択肢の幅を広げれば斬新な回答が、狭めれば無難で一般的な回答が出やすくなります。
Candidate Count
一度の質問で、AIに複数の回答パターンを同時に出してもらう機能です。 これは 「アイデア会議で『A案、B案、C案のように、複数の選択肢を一度に出してください』とお願いする」 のと同じです。様々な角度からの回答を比較検討したいときに便利です。
また生成AI側で機能向上のために勝手にA案・B案を出してきてより期待に沿う回答を選ばせることで回答精度を上げていくこともあります。
まとめ:生成AIを使いこなすための第一歩
これらの用語を理解することで、生成AIがどのように情報を処理し、回答を生成しているのかが少し見えてきたのではないでしょうか。最初は難しく感じるかもしれませんが、実際に使っていくうちに自然と身についていきます。
生成AIは、あなたの強力なアシスタントやエージェントになり得ます。まずは気軽に触ってみて、様々なプロンプトを試しながら、その可能性を体験してみてください。
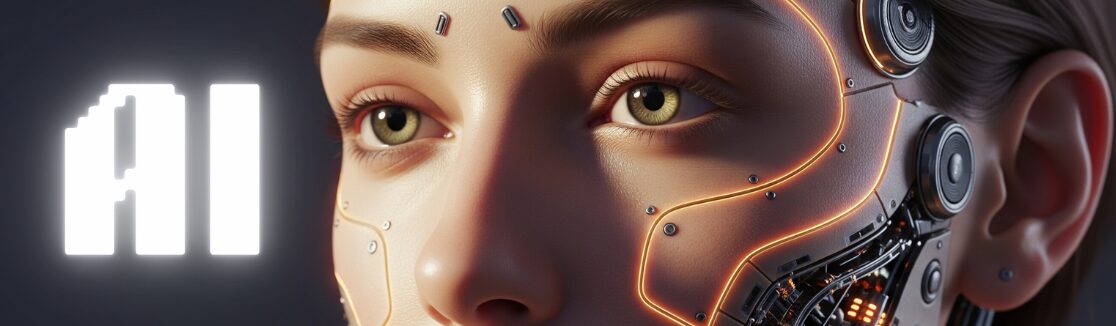



コメント